親知らず抜歯後の食事選びに迷わない!回復を促進する食品と避けるべき食品
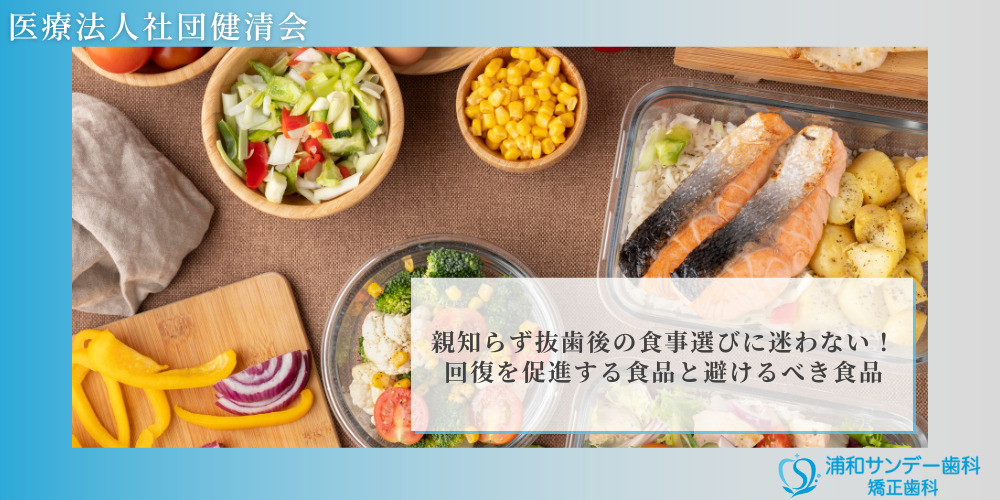
浦和区浦和駅から徒歩5分の歯医者・矯正歯科「浦和サンデー歯科・矯正歯科」です。
親知らずの抜歯は、多くの方が経験する外科処置ですが、術後の回復において特に気になるのが食事ではないでしょうか。抜歯後の傷口を早く治し、痛みや腫れを最小限に抑えるためには、適切な食事選びが非常に重要となります。この記事では、親知らず抜歯後の食事に関する疑問や不安を解消し、時期ごとにおすすめのメニューや避けるべき食品、さらには日常生活で気をつけたいポイントまで詳しく解説します。ぜひ、この記事を参考に、安心して回復期間を過ごし、健やかな毎日へと戻るための一助にしてください。
はじめに:親知らず抜歯後の食事が回復を左右する理由
親知らずの抜歯は外科処置であり、お口の中には少なからず傷ができます。この傷が適切に治癒するためには、食事が非常に重要な役割を果たします。抜歯後の傷口には「血餅(けっぺい)」と呼ばれる血の塊が形成され、これがかさぶたのような役割をして、傷口を保護し、骨や歯肉が再生するための足がかりとなります。不適切な食事や食べ方をしてしまうと、この血餅が剥がれてしまい、治癒が遅れたり、場合によっては強い痛みを伴う「ドライソケット」と呼ばれる状態になるリスクが高まります。
また、食事は単に空腹を満たすだけでなく、身体の回復に必要な栄養素を補給する手段でもあります。抜歯後の体は、傷の治癒や炎症の抑制のために多くのエネルギーと栄養を必要としています。特に、ビタミンやミネラル、タンパク質などは、細胞の再生や免疫機能の維持に不可欠です。栄養バランスの取れた食事を心がけることで、体の治癒力を最大限に引き出し、回復を早めることにつながります。逆に、栄養が偏った食事は回復を遅らせる原因にもなりかねません。
このように、抜歯後の食事は単なる一時的な制限ではなく、傷口の保護、感染予防、そして全身の回復を促進するための重要な要素なのです。正しい知識を持って食事を選ぶことが、快適でスムーズな回復への第一歩となります。
いつから食事ができる?抜歯後の食事開始のタイミング
親知らずの抜歯後、いつから食事ができるのかという疑問は多くの方が抱くことでしょう。最も重要なのは、麻酔が完全に切れてから食事を始めることです。抜歯処置の際に使用された麻酔は、通常2〜3時間程度で効果が切れることが多いですが、個人差もありますので、ご自身の感覚で麻酔が完全に切れたことを確認するようにしてください。
麻酔が効いている状態でお食事をしてしまうと、お口の中の感覚が鈍くなっているため、誤って頬の内側や唇、舌を噛んでしまう危険性があります。これにより、新たな傷を作ってしまい、痛みが増したり、出血が起こったりと、回復が遅れる原因となることがあります。麻酔が完全に切れてから、お口の中の感覚が元に戻ったことを確認してから、ゆっくりと食事を始めるようにしましょう。最初の食事は、後述する柔らかいものを少量から試すのがおすすめです。
【時期別】回復を助けるおすすめの食事メニュー
親知らずの抜歯後、どのタイミングでどのような食事をすれば良いのかは、多くの方が抱える疑問の一つです。このセクションでは、抜歯直後の痛みや腫れが強い時期から、徐々に通常の食事に戻していくまでのステップを、時期ごとにおすすめのメニューとともにご紹介します。適切な食事を選ぶことで、回復をサポートし、食事のストレスを軽減しながら、安全に抜歯後の期間を過ごせるようになります。
抜歯当日~3日目:痛みや腫れが強い時期の食事
親知らず抜歯後の当日を含めた3日間は、特に痛みや腫れが強く出やすい時期です。特に親知らずの抜歯では、抜歯後2日目、つまり48時間後に腫れがピークに達することが多く、口を開けるのが困難になることもあります。この時期の食事は、傷口に余計な負担をかけず、なおかつ必要な栄養をしっかりと摂取することが最も重要になります。
基本的には、よく噛む必要がない「柔らかいもの」、熱すぎず冷たすぎない「人肌程度の温度のもの」を選ぶようにしましょう。刺激の少ない優しい味付けで、スムーズな回復を促す食事を心がけることが大切です。
おかゆ・ヨーグルトなどの流動食・半固形食
抜歯当日〜3日目の食事として特におすすめなのは、流動食や半固形食です。例えば、おかゆや雑炊は、水分が多く米粒が柔らかく煮込まれているため、ほとんど噛まずに飲み込むことができます。出汁を効かせれば食欲がないときでも食べやすく、体力の回復に必要な炭水化物を効率よく摂取できます。
また、ポタージュスープ、ヨーグルト、豆腐、茶碗蒸しなども非常に適しています。ポタージュスープは、野菜を煮込んでミキサーにかけることで、栄養を豊富に含みながらもなめらかな口当たりになります。ヨーグルトは冷たくて口当たりが良く、腸内環境を整える効果も期待できます。豆腐や茶碗蒸しは、消化が良くタンパク質も摂取できるため、傷口への負担をかけずに栄養補給が可能です。
これらの食事を用意する際は、具材を小さく刻んだり、ミキサーにかけるなどして、よりなめらかな状態に調理する工夫をすると良いでしょう。温度も熱すぎず冷たすぎない人肌程度に調整し、傷口への刺激を避けることが大切です。
ゼリー飲料やスープで栄養を補給する
抜歯直後で食欲がない、または口が開けにくいといった理由で固形物が食べられない場合でも、栄養補給は非常に重要です。そのような時には、ゼリー飲料や栄養補助スープを上手に活用することをおすすめします。これらの製品は、手軽にカロリーやビタミン、ミネラルを補給でき、体力維持に役立ちます。
市販のゼリー飲料を選ぶ際は、タンパク質やビタミンが豊富に含まれているものを選ぶと良いでしょう。また、ご自宅で簡単に作れる栄養スープとして、鶏肉や野菜をじっくり煮込み、裏ごししたりミキサーにかけたりして作るポタージュ状のスープもおすすめです。これらの工夫によって、回復期に必要な栄養素を無理なく摂取し、体力の低下を防ぐことができます。
抜歯後4日目~1週間:少しずつ固形物に慣れる時期の食事
抜歯後4日目から1週間にかけては、痛みや腫れが少しずつ和らいでくる時期です。この期間は、抜歯直後の流動食中心の食事から、徐々に形のある固形物へと移行していく段階となります。まだ傷口は完全に塞がっているわけではないため、油断は禁物です。
「柔らかく調理された固形物」を選ぶことを基本とし、噛む機能の回復を促しながらも、傷口に負担をかけないようなメニューを意識しましょう。急に硬いものや刺激の強いものを食べ始めるのではなく、体の状態に合わせて慎重に食事内容を調整していくことが、順調な回復につながります。
柔らかく煮込んだうどんや煮魚
抜歯後4日目から1週間の食事として、柔らかく煮込んだうどんや煮魚は特におすすめです。うどんは柔らかく煮込むことで、咀嚼の負担を大幅に減らすことができます。具材として、鶏ひき肉や柔らかく煮た野菜を細かく刻んで加えると、栄養バランスも良くなります。ただし、麺類をすする行為は血餅が剥がれる原因となる陰圧を発生させるため、箸で少しずつ口に運ぶようにしましょう。
煮魚であれば、カレイやタラといった白身魚の煮付けが適しています。身が柔らかく、箸で簡単にほぐれるため、傷口に負担をかけずにタンパク質を摂取できます。味付けは薄めにし、熱すぎないよう人肌程度に冷ましてから食べるようにしてください。マカロニグラタンなども、柔らかいマカロニとホワイトソースが食べやすく、チーズで栄養も補給できます。
これらの料理は、比較的少ない力で食べられるため、顎への負担を軽減しながら、多様な栄養素を取り入れることができます。食事のレパートリーを増やし、回復期の食生活を豊かにするためのヒントとして活用してください。
豆腐ハンバーグや卵料理
抜歯後の回復期において、体力の回復には良質なタンパク質の摂取が不可欠です。しかし、肉類などの固いタンパク源はまだ食べにくいことがあります。そこで、豆腐ハンバーグや卵料理が非常に有効な選択肢となります。
豆腐ハンバーグは、鶏ひき肉と豆腐を混ぜて作ることで、通常のハンバーグよりも格段に柔らかく、口の中で崩れやすくなります。さらに、あんかけにするなどの工夫を加えれば、喉越しも良くなり、より食べやすくなります。また、スクランブルエッグやだし巻き卵、卵豆腐なども、噛む力が弱っていてもスムーズに食べられ、手軽に良質なタンパク質を摂取できる優れたメニューです。
これらの料理は、消化にも良く、身体が回復に必要な栄養素を効率よく吸収するのを助けます。味付けは薄味を心がけ、刺激を与えないように配慮しながら、無理なくタンパク質を補給し、体力回復につなげていきましょう。
抜歯後1週間以降:通常の食事に戻す時期の注意点
抜歯後1週間が経過すると、多くの場合、痛みや腫れはかなり落ち着き、傷口も安定してくる時期です。この頃には、これまで制限していた食事内容を、少しずつ通常の食事に戻していくことが可能になります。しかし、完全に傷口が塞がっているわけではないため、焦って硬いものや刺激物を一度に再開するのは避けましょう。
大切なのは、自分の体の状態と傷口の様子をよく観察しながら、慎重に食事内容をステップアップしていくことです。まずは柔らかめの固形物から始め、少しずつ硬さのあるものへと移行していきましょう。万が一、痛みや違和感を感じた場合は、無理せずに再び柔らかい食事に戻すなど、柔軟に対応することが大切です。この期間も、無理はせず、体の声に耳を傾けるようにしてください。
回復を妨げる!抜歯後に絶対に避けるべき食品・飲み物
親知らずの抜歯後、順調な回復のためには、摂取する食品だけでなく、避けるべき食品や飲み物についても理解しておくことが非常に大切です。これまでのセクションでは、抜歯後の時期ごとにおすすめの食事をご紹介してきましたが、ここからは、なぜ避けるべき食品があるのか、その具体的な理由を明確にしていきます。傷口への物理的な刺激、血行促進による再出血のリスク、そして治癒に不可欠な血餅(けっぺい)が剥がれてしまうリスクなど、抜歯後のトラブルを防ぐために知っておくべき危険性をこれから詳しくご説明します。
傷口を刺激する硬いもの・辛いもの
抜歯後の傷口は非常にデリケートな状態です。そのため、硬い食べ物は傷口を物理的に刺激し、痛みや治癒の遅れを招く大きな原因となります。たとえば、おせんべいやナッツ類、フランスパンのような硬いパン、さらには揚げ物の衣といったサクサクとした食感のものは、噛むことによって傷口に直接当たり、炎症を悪化させたり、出血を引き起こしたりするリスクがあります。これらの食品は、抜歯後しばらくは避けるようにしてください。
また、味の濃いものや刺激の強い食品も、抜歯後の傷口には負担となります。カレーやキムチなどの香辛料が効いた辛い料理、レモンやグレープフルーツなどの酸味の強い柑橘類、そしてお酢を多く使った料理などは、傷口にしみて強い痛みを引き起こす可能性があります。刺激物によって傷口の治癒が妨げられることもあるため、できるだけ避けて、消化が良く優しい味付けの食事を心がけるようにしましょう。
血行を促進するアルコールや熱い飲み物
抜歯後、血行を過度に促進する行為は、再出血や腫れの原因となるため、特に注意が必要です。アルコールには血管を拡張させる作用があるため、抜歯後の飲酒は、せっかく止血した傷口から再び出血したり、すでに腫れている部分の腫れを悪化させたりするリスクがあります。痛みが増す原因にもなりかねません。
同様に、熱すぎるスープやコーヒー、紅茶などの飲み物も、口の中の血行を良くしてしまうため、控えるべきです。温かいものを摂取する際は、必ず人肌程度に冷ましてからゆっくりと飲むようにしてください。一般的に、抜歯後は最低でも2~3日間、できれば1週間程度はアルコールの摂取を控えることをおすすめします。
血餅が剥がれる原因になる炭酸飲料やすする麺類
抜歯後の傷口には「血餅(けっぺい)」という血の塊ができます。この血餅は、かさぶたのような役割を果たし、傷口を保護して治癒を促す非常に重要なものです。しかし、特定の行為や食品によって、この血餅が剥がれてしまうリスクがあります。
その代表的なものが、ストローを使って飲み物を飲む行為や、ラーメンやそばなどの麺類を強く「すする」行為です。これらの動作は、口の中に「陰圧(いんあつ)」と呼ばれる負圧を生み出し、この陰圧によって血餅が吸い出されて剥がれてしまうことがあります。血餅が剥がれて骨が露出すると、「ドライソケット」という激しい痛みを伴う状態になる可能性があり、治癒が大幅に遅れてしまいます。
また、炭酸飲料も口の中で発泡する際に、血餅を剥がす原因となることがあるため、抜歯後しばらくは避けるべきです。飲み物を摂取する際は、コップから直接、ゆっくりと飲むように心がけましょう。これらの注意点を守ることで、ドライソケットのリスクを減らし、順調な回復を促すことができます。
抜歯後の食事で守るべき4つの基本ルール
親知らずの抜歯後の回復をスムーズに進めるためには、食事の選び方だけでなく、食べ方や過ごし方にも気を配る必要があります。ここでは、これまでお伝えしてきたポイントを踏まえ、抜歯後の生活で特に守っていただきたい4つの基本ルールをご紹介します。これらのルールを実践することで、痛みや腫れといったトラブルを防ぎ、安心した回復期間を送ることができるでしょう。
ルール1:麻酔が切れてから食べる
抜歯後の食事に関する最も基本的なルールは、麻酔が完全に切れてから食事を始めることです。親知らずの抜歯後は、長時間にわたって麻酔が効いていることが多く、その間は口の中の感覚が鈍くなっています。この状態で食事をしてしまうと、意図せず頬の内側や舌、唇などを強く噛んでしまい、新たな傷や出血を引き起こす危険性があります。
麻酔が切れるまでの時間は個人差がありますが、一般的には2~3時間程度が目安です。ご自身の感覚で、口の中が普段の状態に戻ったことをしっかりと確認してから、ゆっくりと最初の食事を始めてください。無理に早い段階で食事を摂ろうとせず、焦らず待つことが、安全な回復への第一歩となります。
ルール2:抜歯した歯の反対側で噛む
食事をする際には、抜歯した側とは反対側の歯を使って噛むように心がけましょう。抜歯したばかりの傷口は非常にデリケートであり、食べ物が直接触れることで痛みが生じたり、細菌感染のリスクが高まったりする可能性があります。また、噛む動作による圧力も傷口に負担をかける原因となります。
無意識のうちに抜歯側で噛んでしまうこともあるため、食事中は意識して反対側を使うように注意が必要です。もし食べ物が傷口に触れてしまった場合は、無理に取ろうとせず、食後にコップの水を軽く含んで優しくゆすぐ程度にとどめてください。このような小さな工夫が、傷口の保護とスムーズな回復につながります。
ルール3:ストローを使わない・強くすすらない
抜歯後の飲食物の摂取において、特に注意が必要なのが、ストローの使用や麺類などを強くすする行為です。これらの行為は、口の中に「陰圧」と呼ばれる負の圧力を生じさせます。この陰圧が、抜歯窩(ばっしか)と呼ばれる歯を抜いた後の穴を塞いでいる「血餅(けっぺい)」を吸い上げて剥がしてしまう大きな原因となるのです。
血餅は、抜歯後の傷口を保護し、骨や歯茎が再生するための土台となる、かさぶたのような非常に重要なものです。この血餅が剥がれてしまうと、骨が露出し、激しい痛みを伴う「ドライソケット」という状態を引き起こします。ドライソケットは治癒に時間がかかり、日常生活に大きな支障をきたすため、細心の注意が必要です。飲み物を飲む際はコップから直接、静かに口に運ぶようにし、麺類もすすらずに短く切って食べるなど、口の中に陰圧がかからない工夫を心がけましょう。
ルール4:人肌程度の温度のものを食べる
抜歯後の食事では、飲食物の温度にも配慮が必要です。熱すぎるものは、血管を拡張させて血行を促進するため、再出血や腫れを助長する原因となる可能性があります。特に抜歯直後のデリケートな時期は、熱いスープや飲み物、料理は避けるべきです。
一方で、冷たすぎるものも、傷口を刺激して痛みを引き起こすことがあります。そのため、極端に冷たいアイスクリームや氷なども、抜歯直後は避けた方が無難です。食事や飲み物は、体温に近い人肌程度の温度に冷ましてから摂取するようにしましょう。適切な温度管理は、傷口への刺激を最小限に抑え、余計なトラブルを防ぎながら回復を促すために非常に重要です。
食事以外も大切!抜歯後の回復を早めるための生活習慣
親知らずの抜歯後の回復を早めるためには、食事の管理だけでなく、日々の過ごし方も非常に重要です。適切な口腔ケア、身体活動の制限、痛みや腫れへの対処法など、食事以外の生活習慣にも気を配ることで、トラブルを防ぎ、より早く快適な状態に戻ることができます。これらの習慣を食事の注意点と併せて実践することで、抜歯後の回復期間をスムーズに乗り越えましょう。
口腔ケア:優しいうがいと抜歯部位を避けた歯磨き
抜歯後の口腔ケアは、傷口の感染を防ぎ、治癒を促進するために非常に大切です。ただし、自己流のケアはかえって傷口に負担をかける可能性があるため、正しい方法を実践しましょう。
まず、うがいについては、抜歯当日は極力控えるようにしてください。翌日からは、処方されたうがい薬や常温の水を口に含み、ブクブクと強くうがいをするのではなく、優しくゆすぐ程度に留めることが重要です。強くうがいをすると、傷口を保護している血餅(けっぺい)が剥がれてしまい、ドライソケットと呼ばれる激しい痛みを伴う状態になるリスクがあるため、注意が必要です。
次に歯磨きですが、抜歯した部位とその周辺は、最低でも抜歯後2~3日は直接磨かないようにしてください。それ以外の健康な歯は、通常通り丁寧に磨くことで、お口の中を清潔に保ちましょう。抜歯部位の傷口が安定してきたと感じる抜歯後1週間頃からは、毛先の柔らかい歯ブラシを使って、傷口に触れないように優しく磨き始めることができます。もし不安な場合は、かかりつけの歯科医師に相談して指示を仰ぐのが最も安全です。
日常生活:激しい運動・長風呂・喫煙は控える
抜歯後の順調な回復には、安静に過ごすことが非常に重要です。激しい運動や長風呂、飲酒、喫煙といった血行を促進する行為は、再出血や腫れの悪化、痛みの増強を引き起こす原因となるため、控えるようにしてください。
具体的には、抜歯後2〜3日間は、運動を控え、シャワー程度で済ませるようにしましょう。湯船に浸かって体が温まりすぎると、血行が良くなりすぎて再出血しやすくなる可能性があります。また、アルコールも血管を拡張させる作用があるため、抜歯後最低でも2〜3日、可能であれば1週間程度は控えることが推奨されます。
喫煙は、血流を悪化させて傷の治りを著しく遅らせるだけでなく、感染のリスクも高めます。抜歯後の治癒過程において、喫煙は最も避けるべき行為の一つです。傷口が完全に塞がるまでの最低1週間は禁煙し、できればこの機会に禁煙を検討することをおすすめします。
痛みや腫れへの対処法:痛み止めと冷却
親知らずの抜歯後には、痛みや腫れを経験することがほとんどです。これらの症状を適切に管理することで、快適に回復期間を過ごすことができます。
「痛み」に対しては、歯科医院で処方された鎮痛薬を指示通りに服用することが最も効果的です。痛みが強くなる前に服用することで、痛みをコントロールしやすくなります。市販薬で対応しようとせず、必ず処方された薬を正しく使いましょう。
「腫れ」は抜歯後2日目がピークに達することが多いです。腫れを抑えるためには、抜歯当日から翌日にかけて、濡れタオルや冷却シートなどで頬の外側から優しく冷やすことが有効です。ただし、氷を直接当てたり、長時間冷やしすぎたりすると、血行が悪くなり傷の治りを妨げてしまう可能性があるため注意してください。冷やすことで一時的に腫れや痛みが和らぎますが、冷やしすぎないように適度に行うことが大切です。腫れは誰にでも起こりうる自然な反応であることを理解し、過度に心配しすぎないようにしましょう。
こんな時はどうする?抜歯後のトラブルと対処法
親知らずの抜歯後は、どれだけ注意して過ごしていても、予期せぬトラブルが起こる可能性もゼロではありません。あらかじめ、どのような症状が起こりうるのか、その際にどのように対処すれば良いのかを知っておくことで、いざという時も冷静に対応できます。このセクションでは、抜歯後によく見られるトラブルの症状と、ご自身でできるセルフケア、そして歯科医院に相談すべきケースの見極め方について解説していきます。
食べ物が傷口に入ってしまった場合
抜歯後の傷口に食べ物のカスが挟まってしまうことは、多くの方が経験する不安の一つではないでしょうか。しかし、焦って指や爪楊枝などで無理に取り除こうとするのは非常に危険です。傷口を傷つけてしまったり、細菌感染の原因になったりする可能性があるため、絶対に避けてください。
もし食べ物が傷口に入ってしまった場合は、食後にコップの水を口に含み、静かにゆすぐ程度で様子を見てください。ブクブクと強いうがいをしてしまうと、せっかくできた血餅が剥がれてしまうリスクがありますので注意が必要です。それでも気になる場合や、痛みがある場合は、自己判断せずに、抜歯を受けた歯科医院に連絡して指示を仰ぐのが最も安全で確実な方法です。強い痛みが続く(ドライソケットの可能性)
抜歯後、2~3日経っても痛みが治まらず、むしろ強くなったり、ズキズキとした耐えがたい痛みが続いたりする場合は、「ドライソケット」の可能性があります。ドライソケットとは、抜歯窩(歯を抜いた穴)を覆うはずの血餅が何らかの原因で剥がれ落ちてしまい、骨がむき出しになってしまう状態のことです。
骨が外気に触れることで、非常に強い痛みを引き起こし、市販の痛み止めでは効果が得られにくいことも特徴です。もしドライソケットが疑われる場合は、自己判断で我慢せずに、すぐに抜歯を行った歯科医院を受診してください。歯科医院では、傷口の洗浄や薬の塗布、保護材の挿入などの処置によって痛みを和らげ、治癒を促す治療が行われます。早期に適切な処置を受けることで、痛みの軽減と回復の促進につながります。
出血が止まらない場合
抜歯後、唾液に少し血が混じる程度の出血は、数日間続くことがあります。これは異常なことではなく、傷口が治っていく過程で起こる自然なことですので、過度に心配する必要はありません。
しかし、もし鮮血がだらだらと止まらなかったり、口の中に血が溜まってくるような出血が見られたりする場合は、清潔なガーゼやティッシュを小さく丸めて、抜歯した穴の上にしっかりと当て、20~30分ほど強く噛んで圧迫止血を試みてください。この圧迫によって止血が促進されることが多いです。それでも出血が止まらない場合は、夜間でも遠慮せずに、速やかに抜歯を受けた歯科医院へ連絡し、指示を仰ぐようにしてください。
まとめ:正しい食事で親知らず抜歯後の不安を解消し、順調な回復を目指そう
親知らずの抜歯は多くの方が経験される歯科治療ですが、術後の痛みや腫れ、特に食事に対する不安を感じる方も少なくありません。しかし、この記事でお伝えしたように、時期に応じた適切な食事選びと、いくつかの基本的な生活習慣を守ることで、これらの不安は大きく軽減できます。抜歯直後から1週間程度は、傷口に負担をかけない柔らかい食事を心がけ、徐々に通常の食事へと戻していくステップを踏むことが大切です。
この記事で得た知識を実践することで、痛みや腫れを最小限に抑え、スムーズな回復が期待できます。ぜひ、これらの情報を活用して、抜歯後もストレスなく、前向きな気持ちで回復期間を過ごしてください。
不安な点は自己判断せず、かかりつけの歯科医師に相談を
この記事では親知らず抜歯後の食事や生活習慣に関する一般的な情報を提供してきましたが、個々の抜歯の状況やお口の状態は人それぞれ異なります。そのため、もし少しでも不安なことや、ご自身の回復状況に異常を感じた場合は、決して自己判断したり、放置したりせずに、速やかに抜歯手術を受けた歯科医院にご相談ください。かかりつけの歯科医師に相談することが、安全で確実な回復への一番の近道です。
少しでも参考になれば幸いです。
本日も最後までお読みいただきありがとうございます。
監修者
日本大学歯学部卒業後、現在に至る。
【略歴】
・日本大学歯学部 卒業
さいたま市浦和区浦和駅から徒歩5分の歯医者・矯正歯科
『浦和サンデー歯科・矯正歯科』
住所:埼玉県さいたま市浦和区仲町1丁目10-1 PORAMビル 1F
TEL:048-826-6161
